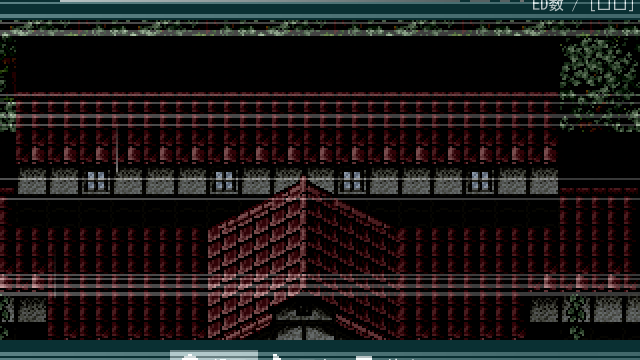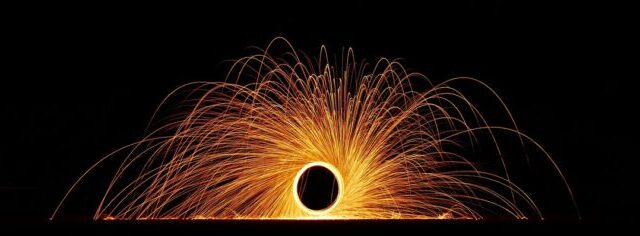ボクは読み物が好きです。
ネットの記事から小説や雑誌まで読み物なら何でも好きです。
書くことも好きです。
自分の頭のなかにあるものを文章化して吐き出すと、とても気持ちが良いです。
このブログでは掌編小説(しょうへんしょうせつ、短編よりも短い小説、ショートショートともいう)という形で、頭のなかにあるものを吐き出そうと思います。
楽しんでいただければ幸いです。
スレチガウモノ
ボクの友だちが小学生だったころの話である。
彼は野球部に所属しており、その日も遅くまで練習に励んでいた。
日も暮れかけ、辺りも暗くなってきたころ、ようやく練習が終わり、彼は友人たちと急いで家路へついた。
彼らの家路には2種類あり、村の大通りと、村の外れの墓地を通る道があった。
クタクタの身体で、もう動きたくなかった彼らは、近道である墓地を通って帰ることを選択した。
いつも一緒に帰るメンバーは彼も含めて4人である。
村はずれの墓地はとても狭く、左右に墓石や地蔵が並んでいた。
必然的に横に並んで歩けなくなるので、彼らは一列に並んで歩くことになる。
薄暗く不気味な墓地で誰も先頭を歩きたがらない。
こういうときは、いつもジャンケンで順列を決めることにしていた。
幸いにも彼は列の先頭から3番目になった。
1番前も嫌だが、1番後も嫌である。
彼は良い位置に自分がおさまったとほくそ笑んでいた。
まるで某RPGゲームのように、一列で狭い道を進む。
ちょうど道の真ん中ほどに来た辺りだろうか、彼は前から歩いて来る白い影を見た。
さらに道を進みながら白い影に近づいて行くと、白い着物を着た女性であることがわかった。
彼は、直観した。これは明らかに現代の人間ではない。
その佇まいや雰囲気から現代の人間ではありえない。
そもそもこんな時間にわざわざ着物で、墓地を一人で歩く女性などいるものだろうか。
考えている間に、どんどん女性との距離が縮まっていた。
縮まる距離に比例して、彼の心臓は痛いくらいに鼓動していた。
だが、それ以上に彼を混乱させたのが、自分の前を歩く友人たちであった。
一列にならなければ歩けないほど狭い道である。
しかし友人たちは前から女性が歩いてくるにも関わらず、一向に道を譲るような気配がない。
もしかすると女性の姿は自分にしか見えていないのではないか。
恐怖と混乱で頭がいっぱいになったとき、いよいよ女性とすれ違う距離まで近づいていた。
ぶつかる、そう思った彼だったがその予想は外れた。
前の友人2人を女性がすり抜けたのである。
そして、女性は彼もすり抜けていった。
すり抜ける際に、彼は女性と目が合った。
女性は薄っすらと笑みを浮かべていた。
さらにむせ返るような線香の香りがした。
鼻の奥が痛み、数秒間ほど嗅覚を失うような強烈な香りだった。
彼はすぐに後ろを振り向くと、その女性は消えていた。
その場で、彼は友人たちに女性のことを問いただしたが、予想通り女性が見えているのは自分だけだった。
これはボクの友人が体験した話を、ボクが肉付けしたものです。
ちなみに、すれ違った女性にはしっかりと足が生えていて、ちゃんと歩いていたそうです。